出生前・周産期心理学とは
出生前・周産期心理学をワインスタイン博士は著書の中でこのように定義しています。
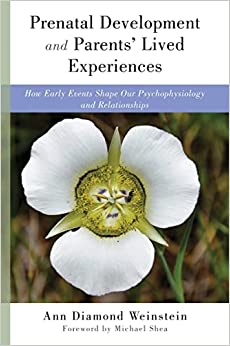
「出生前・周産期心理学とは、受胎、子宮内での時間、出生中および出生後の経験、出生後1年までの養育者や家族システムとの経験など、人間の発達における最も初期の時期について学際的に研究する学問です。 発生学、形態形成、生物工学、進化生物学、心理生理学、行動周産期学、神経生物学、感情神経科学、愛着、外傷学など様々な分野の理論や研究が、この重要な発達期の体験が個人に与える影響を探求するための基礎となる。これらの分野の知識は、私たちの最も初期の経験が身体的、認知的、社会的、感情的に与える影響と、それらがどのように生涯にわたって私たちの発達、行動、健康を形成する永続的な反応パターンを形成するかを明らかにするものである。」
アン・ダイアモンド・ワインスタイン著 Prenatal Development and Parents’ Lived Experiences: How Early Events Shape Our Psychophysiology and Relationships (W.W. Norton & Company, 2016)P5
ここではその出生前・周産期心理学の歴史をご紹介します。
出生前・周産期心理学の主な歴史
1912年:ザビーナ・シュピールライン 論文『生成の原因としての破壊』を発表
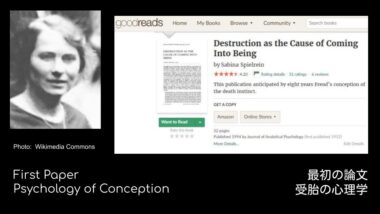
シュピールラインはこの論文の中で
「我々がこれらの破壊的、再構築的なプロセスを感じることがないというのはありえない」
と発表し、生まれる以前の体験を記憶していると発表した最初の人物である。
1924年:オットー・ランク 『出生外傷』を出版

フロイトの弟子であったオットー・ランクは、人間がこの世に生まれてくることそのものが外傷(トラウマ)の体験であると述べた。
神経症や精神病が「出生時の外傷の再現である」と発表した。
スタニスラフ・グロフ LSDセラピー(ホロトロピック・ブレスワーク)

トランスパーソナル心理学の創設者でもあるスタ二スラフ・グロフは、20代の頃に当時まだ合法であったLSDチェコスロバキアで3000以上もの臨床研究を行い、サイケデリック・セラピーを開発した。受胎を決定してから誕生するまでのプロセスの中で体験してきた感情というのが人格形成に大きな影響を与えている事を発表した。
このセラピーを体験したクライアント達は、日本でいわゆる胎内記憶として一般的に知られている出生時の記憶や前世記憶を含む体験や臨死体験などを経験すると言われている。
1976年:R.D. レイン 『生の事実』を出版

…少なくとも神話や伝説、物語、夢、空想、行動の中に私達の胎内での経験から余韻や波動がこれらに含まれている可能性はあると言えるだろう。
と語っている。
1979年:トマス・バーニー 論文発表
トマス・バーニー博士は、ローマで開催された精神身体医学と産婦人科による国際会議の中で論文「The Psychic Life of the Unborn Child(胎児の超能力的ないのち)」を発表し、R.D.レイン等の世界的に著名な発表者と共に600人程の聴衆の前で初講演を行った。
この講演で発表した内容をベースに、バーニー博士は「胎児は見ている」の原稿を執筆した。
1981年 トマス・バーニー 「胎児は見ている」を出版
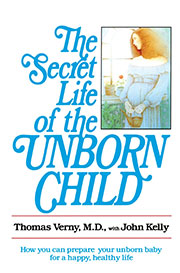
トマス・バーニー 「胎児は見ている」を出版(日本語訳は1982年に出版)& アメリカ横断ブックツアー。
ニューヨークの大手出版社であるサイモン&シュスター社から「胎児は見ている(The Secret Life of the Unborn Child)」は大きな企画として出版され、宣伝活動としてアメリカ横断ツアーを行った。
このブックツアー中にバーニー博士はデイヴィッド・チェンバレン博士と出逢い、交流を深めていった。
1983年:PPPANA – 北米出生前・周産期協会設立
バーニー博士が出席したローマでの国際会議と全米ブックツアーで沢山の研究者や専門家と繋がることが出来たバーニー博士は、チェンバレン博士と共にトロントで第1回北米出生前・周産期心理学会国際会議を開催し、大成功を収めた。
これを受け、PPPANA(北米出生前・周産期心理学協会)は初代会長のバーニー博士と副会長のデイビッド・チェンバレン博士により設立された。
1993年:APPPAH – 出生前・周産期心理学協会に名前を変更
その後、PPPANAからAssociation for Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH)に名称を変更した。
APPPAHの他にもヨーロッパで活動している姉妹組織、
「International Society for Pre- and Perinatal Psychology and Medicine e.V.」
があります。
詳細は海外の研究者、海外の団体・組織をご覧ください。

